今回は素数に関して講義したいと思います。整数問題を解く際にカギとなってくるところです。
一般に言われる整数問題の定石ですが、このうちのひとつだけを用いればよいというのではなく、複数を組み合わせていくことが求められます。今回はこの中でも素数を解説しますが、②の積の形に表したとき素数が出てくるとありがたいことがあります。では、まず素数の定義から見ていきましょう。
素数の定義
$p$が素数であるとは、$p$が1と$p$自身以外に正の約数をもたない2以上の自然数であることをいう。
また、1でも素数でもない自然数を合成数といいます。合成数とは、積の形$pq$で表せるものと覚えている人が多いですが、1を忘れないように注意しましょう。したがって、1は素数ではありません。
次に、素数の定義からこのような素数の性質が言えます。
素数の性質
$a, b$が自然数、$p$が素数のとき、$ab$が$p$の倍数 $\Longrightarrow$ $a, b$の少なくとも一方は$p$の倍数である。
$a, b$が自然数、$p$が素数のとき、$ab$が$p$の倍数 $\Longrightarrow$ $a, b$の少なくとも一方は$p$の倍数である。
では、この性質を用いて素因数分解の一意性を示していきましょう。
素因数分解の一意性
$n\geqq 2$とし、$$n = pqr\cdots = p'q'r'\cdots \Longrightarrow p, q, r, \cdotsとp', q', r', \cdotsは全体として一致する。$$
($p, q, r, \cdots , p', q', r', \cdots$は素数)
$n\geqq 2$とし、$$n = pqr\cdots = p'q'r'\cdots \Longrightarrow p, q, r, \cdotsとp', q', r', \cdotsは全体として一致する。$$
($p, q, r, \cdots , p', q', r', \cdots$は素数)
また、かなり自明に近いですがこのような定理もあります。
素因数分解定理
1以外の自然数は有限個の素因数の積として表される
1以外の自然数は有限個の素因数の積として表される
この定理が主張していることは当たり前のことです。例えば、3は素数である3だけ(1個)からできているし、119なら、119=7$\cdot$17より、素数7と17の2個の積からできています。
さて、素数というのは自然数の中でも特別な数だということはわかったと思います。では、素数はどのくらい存在するのでしょうか?素数に関する研究は昔から行われており、素数が無限に存在することは古代ギリシャ時代にはすでに解決されています。様々な証明が明らかにされていますが、そのうちの一つを紹介しましょう。
素数は無限に存在する
無理数の証明でも背理法は定石ですが、やはり否定形の証明では背理法が有効ですね。
(補足) 一方、まったく異なる証明をした人がいてそれはオイラーです。
素数の逆数の和 : $\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}+\cdots$
を考え、この無限級数が無限大に発散することを示し、素数が無数にあることを証明しました。
を考え、この無限級数が無限大に発散することを示し、素数が無数にあることを証明しました。
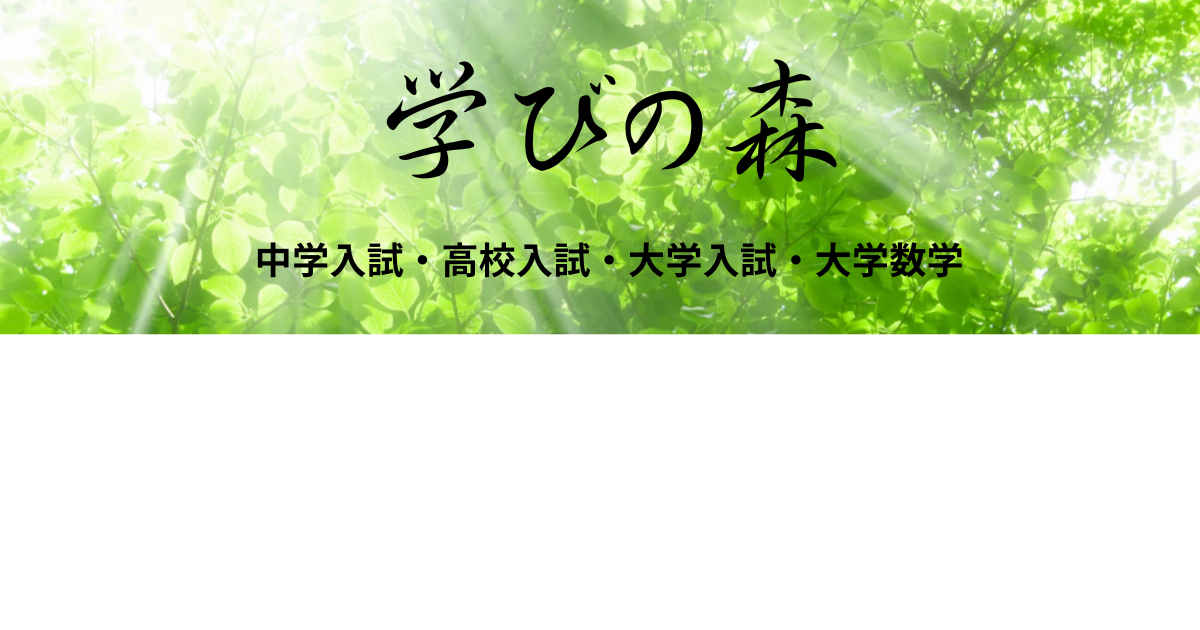

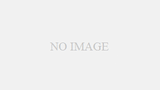
コメント